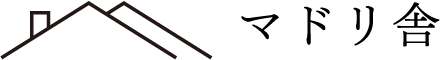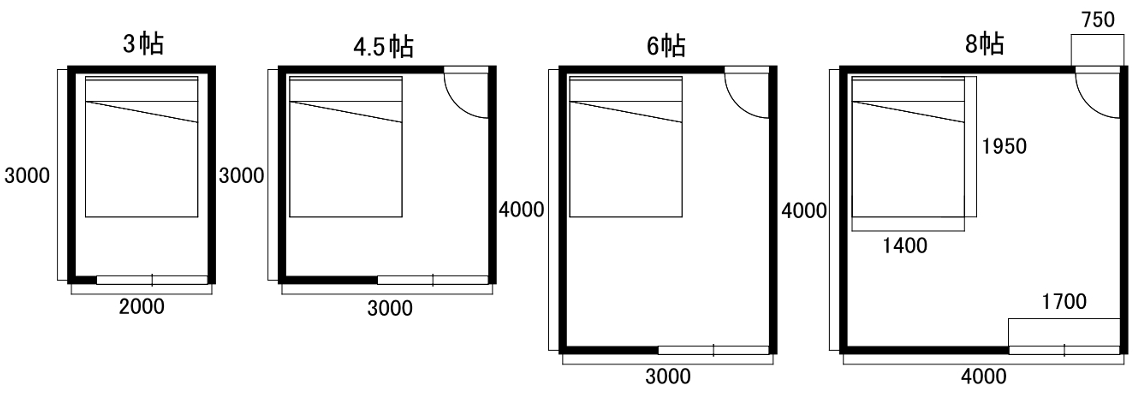設計性能評価と建設性能評価の違い
設計性能評価と建設性能評価の違い・評価の時期について簡単にまとめました。ご覧ください。
これらの評価は、住宅性能表示制度に基づき実施されます。同制度は、平成12年4月1日施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で定められ、住宅の基本性能を第三者機関が国の基準に基づいて評価します。評価機関は異っても方法と表示は統一されています。
品確法では、以下も定められました。
• 新築住宅の基本構造部分に10年の瑕疵担保責任を義務化
• 住宅トラブル解決のための紛争処理機関の整備
平成27年7月には「建築物省エネ法」により制度の基準が改正され、劣化軽減、温熱環境・エネルギー消費量、音環境が見直されました。
住宅性能評価では「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」が交付されます。設計性能評価は設計段階で、建設性能評価は施工中や完成時に実施されます。いずれも10分野で評価されます。
• 構造の安定:地震時の耐久性を等級で評価
• 火災時の安定:避難の安全性や延焼のしにくさを検査
• 劣化の軽減:建物の劣化を遅らせる対策
• 維持管理・更新の配慮:設備の点検・補修のしやすさ
• 温熱環境・エネルギー消費量:省エネ性能と断熱性能
• 空気環境:ホルムアルデヒドや換気設備の有無
• 光・視環境:開口部の大きさや配置の割合
• 音環境:防音性能の評価
• 高齢者等への配慮:バリアフリーの配慮
• 防犯:侵入防止対策
評価は等級で示され、高いほど良いとされます。
まとめ
設計性能評価と建設性能評価を確認することで、物件の特徴や安全性を客観的に把握できます。これにより、信頼できる建物選びが可能になります。