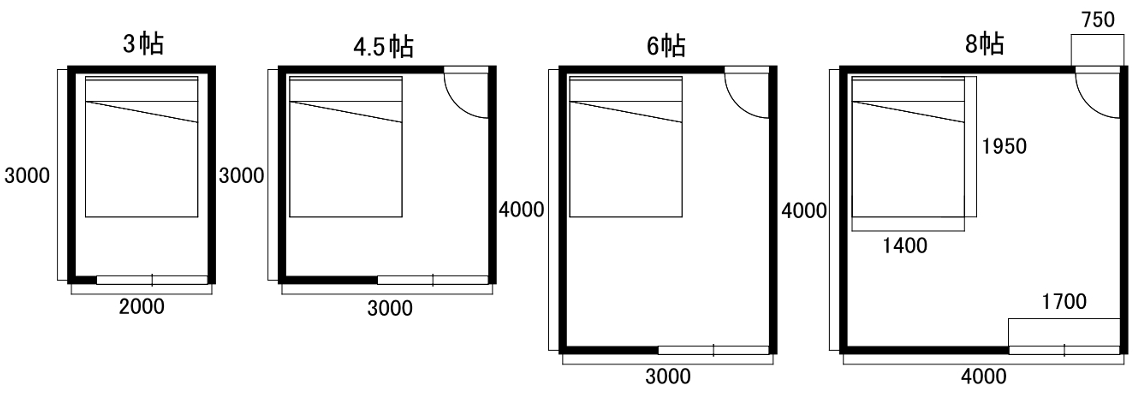八話 「日本人である」というだけで
次の日、僕たちは「バナヒルズ」へ向かうことにした。ネットで調べると山の上に築かれた、まるで中世ヨーロッパを再現したかのようなテーマパークらしい。すでにツアーは手配済み、ハムの彼女の行きたい場所だったのだろう。
ツアーバスに揺られていると隣のベトナム人が僕に気づき、日本語で話しかけてきた。驚いたのはバナヒルズでもまた、別のベトナム人が同じように日本語で話しかけてくる。
学校なのか、会社なのか、彼らはどこかで日本語を学んでいるようだった。きっと日本という国に対する憧れや関心が背景にあるのだろう。
日本では誰からも注目されない小さな会社の経営者である僕が、ここベトナムでは「日本人である」というだけで対等かそれ以上に扱われる場面がある。
グローバルビジネスは大企業のもので、自分には無縁だと思っていた。でもここにはその常識を覆すような感触があった。ニッチな市場では、大きさよりも柔軟さが価値になるとも思えた。
期待が少しずつ現実味を帯びて広がっていく。その一方で本当にうまくいくだろうかという不安も静かに背中に張りついて離れない。
そして翌日、帰国の朝を迎えた。僕はハムに別れを告げ、空港でチェックイン、保安検査、イミグレーションを終え、出国ゲートで搭乗を待つ。窓の外では飛行機が次々と滑走路を走っていく。その光景を眺めながら、頭の中ではこれから始まるかもしれないグローバルビジネスの構想が巡っていた。
今回のダナン滞在は短かったが可能性を感じる旅だった。その理由のひとつ目は経済的な格差。サービスや商品を安く仕入れ付加価値をつけて高く売る。その基本がここでは機能しやすい。ふたつ目はジャパンブランド。僕のような無名の経営者でも日本人というだけで信用される場面が確かにあった。
もちろん課題は山ほどある。資格、税制、現地管理。ひとつひとつ向き合っていかなければならない。それでも事業を始めるために必要な「有利な条件」が揃っている国というのはそう多くはない。ベトナムにはその土台がある。
これから数ヶ月、日本でじっくりとマーケティングを進め、どのようなビジネスモデルを組み上げるかを考えていく。焦らず、確実に。今はその入口にようやく立ったばかりだ。果たしてこの直感は本物なのか。そして自分の力がどこまで通用するのか。高鳴る鼓動の中で不安がそっとささやく。
だが、それ以上に胸を満たしていたのは、まだ見ぬ未来への、静かな期待だった。
つづく。