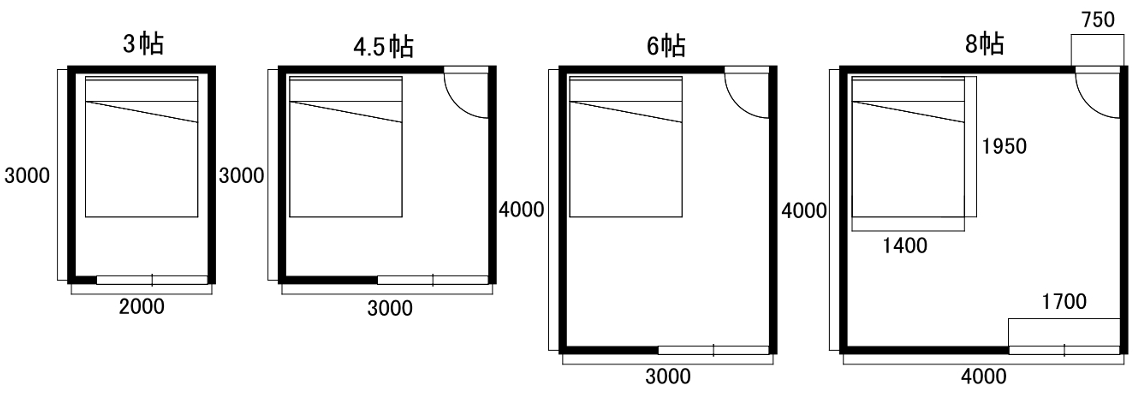私の偏愛--不動産エージェント(賃貸)十一章
ふと壁掛け時計を見ると、午後二時半を指していた。接客が始まってから、もう一時間半。集中力の限界は二時間だろう。長年の経験で体に染みついた勘が、静かに警鐘を鳴らす。あと三十分。期待と不安が胸の底で渦を巻き、じわりと熱を帯びていく。
そのタイミングで、店舗電話が鳴る。前村からだ。
「今、東三方のご案内が終わりました。息子さん、かなり気に入っていますね。お母様もここなら学校まで歩ける距離で安心と喜ばれています。目の前に大型スーパーもあって、印象はすごく良いですよ」
「幹線道路の近さはどう?」
「まったく気にしていないようです。問題ないと思います」
「他に気になる点は? 部屋の広さとか」
「それも特にないですね。おそらく、このまま決まりそうです」
「わかった。引き続き、コミュニケーションを大切にして頑張って」
「了解です」
通話を終えた。店舗の空気がふと静まり返ったように感じた。順調。誰がどう見てもそうだ。だが胸の奥に、小さな石ころのような違和感が残る。
ここまで“固まって”いるのに、なぜ前村は申し込みをいただかないのか?
確かに、クロージングは店舗で私が行う段取りだ。しかし、この物件感度なら、彼がその場で申し込みをいただいていてもおかしくない。むしろ、通常ならそうなっているはずだ。
違和感は消えない。だが、確実に前へ進んでいるのも事実だ。私は一度その石を胸の奥に沈めるように呼吸を整え、これまでの流れを頭の中で巻き戻しクロージングのイメージを高めた。
クロージングで最も警戒すべきは、焦りから「早くしないと無くなりますよ」と口走る“押しの営業”に傾いてしまうことだ。その言葉は、時に強烈な即決力を生む。しかし同時に、客の心に「急かされた」「押された」という影を落とす諸刃の剣でもある。
私が守り続けてきたのは、お客様が自ら“選ぶ”体験を通じ、納得と満足を深めていく「引きの営業」。こちらからせかすのではなく、お客様から自然に「早くしないと無くなりますか?」と聞いていただける状態。そこに持っていくのが理想だ。
そのために、もしも物件が他人で決まってしまった未来をさりげなくイメージしてもらい、選択の重要性を噛みしめてもらう。最終決断はあくまでもお客様自身にある。私たちはプロとしてサポート役に徹する。その軸を一本、心に刺すように私は自分に言い聞かせた。
カウンターに腰かけ、深く息を吸う。午後の光がガラス越しに差し込み、店内の木目をぼんやり照らしていた。落ち着くはずの光なのに、どこかソワソワと心が騒ぐ。そこへ、来期の店長昇格が決まっている高橋が、遠慮がちに近づいてきた。
「先ほど電話でお問い合わせのあったお客様が、物件を見学したいそうです。今から現地案内に行ってもよろしいでしょうか?」
私はお客様の属性を尋ねたが、電話先が騒がしく、よく聞き取れなかったとのこと。見込みの薄いお客様なのか、それとも申し込みのプレッシャーを避けたいのか。現地案内に行くこと自体に理由をつけて断る必要もなかった。
「おっ、いいね。案内中は自分で判断を。頑張って」
「はい、行ってきます」
私は彼の背中を押すと、小走りで店舗を出ていった。その足音が消えると、再び静寂が戻ってくる。
私はこれまで、この店舗と共に、どの瞬間でどう立ち回るかを考え、積み重ねてきた。申し込みを“十”と例えるなら、担当者が“七”の力を出せば、自分が“三”を補う。担当者が“二”しか出せなければ自分が“八”を全力で差し込む。
お客様と担当者の関係ではなく、店舗とお客様との距離感を最優先に整えてきた。その仕組みがあるからこそ、この店は誰がどの時間に立っていても、同じサービスを提供できる。これは理論ではなく、現場の感覚。その日々の積み重ねこそが未来の店舗や私をつくってきた。今日の応対も、きっと未来を形づくるひとつの欠片になる。いや、願わくば“心に刻む一応対”にしたい。
私は前村の帰社を待った。午後の光が少し傾きはじめ、店内の影が長く伸びていた。
つづく。