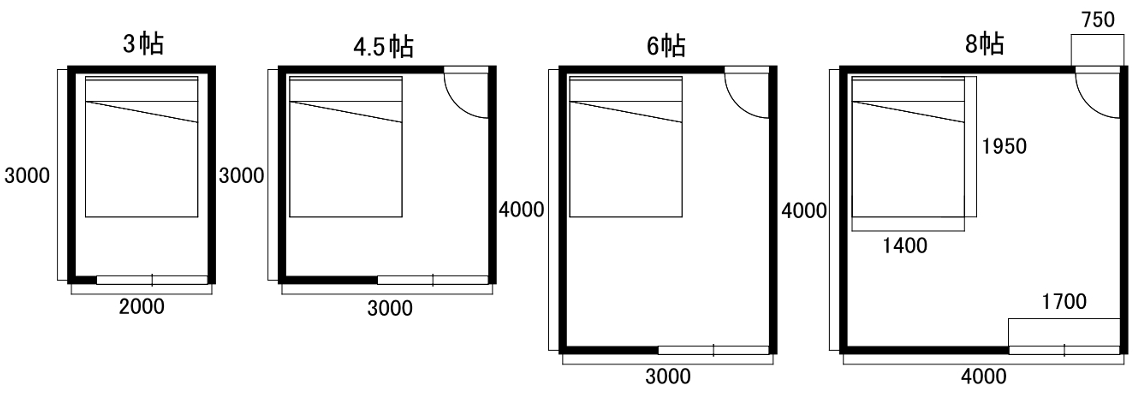私の偏愛--不動産エージェント(賃貸)十二章
お客様を乗せた前村の車が、ゆっくりと駐車場で向きを変える。午後の日差しを受けて、白い車体が一瞬きらりと光る。
前村が先に降り、続いて母親と息子さんが姿を見せた。その表情は、喜びでも不満でもない。まるで湖面のように揺れのない“フラット”。ただ、二人の背筋の張り具合や歩幅の小ささから、どこかに緊張の影が差しているのがわかった。
店に入る瞬間、私を含むスタッフ全員が立ち上がり、初来店時と同様に挨拶を送る。その一斉に整った所作が、場の空気を引き締める。お客様をカウンターへ誘導し、私は満を持して正面に腰を下ろし、案内した物件カードを静かに滑らせた。
「お疲れ様でした。本日ご案内しました物件はこちらとこちらです。実際にご覧いただき、いかがでしたか?」
母親は柔らかく微笑み、言葉を紡ぐ。
「はい、どちらも素敵でした。ただ初生町の物件は学校から少し距離があるのが気になりましたね。それと比べると、東三方の物件は歩いて大学に通えそうで安心です。周りの街並みも賑やかで良かったです」
前村の現地報告と一片の狂いもなく一致している。“しっかりコミュニケーションを取ってきたな”私は心の中でうなずく。ときに報告とお客様の印象が違うことがある。そんなときは応対後になぜそのような現地報告になったのか、たびたびディスカッションした。
私は呼吸を落ち着かせるように、ゆっくりと言葉を続けた。
「山田様がお探しの条件帯は、お母さんと息子さんで多少の違いはありましたが、軸となる条件は“医慶大まで徒歩圏内”、“築浅で外観の良いマンション”、そして特出すべきは“二口ガスコンロ”でしたね」
息子さんは照れたように小さくうなずく。些細な仕草だが、こういう反応は決断の温度を測る貴重なサインになる。そして話を紡ぐ
「実はその条件帯は、医慶大新入生の多くが求める“人気の条件帯”なんです」
母親は軽く目を見開き、息子さんは思わず姿勢を正した。私はさらに
「もし、場所はどこでも構わない、家賃も気にしないということであれば、他にも物件はございます。しかし、そのような条件帯で探される方は多くありません。次に来店される新入生も、おそらく山田様と同じ条件帯で探されると思います」
母親がため息まじりに呟く。
「やっぱり、そうですよね」
その声には“納得”が滲んでいた。私は押し込むのではなく、事実を静かに積み上げる調子で続けた。
「またこの時期、当店だけでも週末は二十件ほどのお申し込みをいただきます。そして医慶大周辺には五社ほど不動産会社があります。当店だけが特別というわけではないと考えると、地域全体では週末だけで百件近くのお申込みが入る計算になります」
「百件もですか?」
「はい。そして条件の良い物件から順に埋まっていきます。山田様が気に入られたこの物件も、その中に含まれていても不思議ではありません」
店内の空気が一瞬静まり返る。数秒の沈黙。ほんの短いはずなのに、妙に長く感じる。そして、その静寂を破ったのは母親だった。
「じゃ、早くしないと無くなりますよね?」
その一言が、胸の奥で静かに着火する。私は思わず心の中で深く頭を下げた。この言葉を引き出すために、送迎から案内、会話、全てのプロセスを積み重ねてきたのだ。
「はい。今は山田様のような新入生の駆け込み時期です。四月上旬入居の物件となると、希少性はかなり高いと思います」
再び沈黙。今度は“決断の前触れ”を含んだ、濃密な沈黙だ。おかしい。母親の表情が、ほんの僅かに曇り始めた。あれほど前向きな温度だったのに、何かが影を落としている。息子さんが母親の袖をつまみ、小声で囁いた。
「お母さん、ここでいいじゃん。無くなっちゃうよ」
焦りではなく、純粋な願い。その声が逆に、母親の迷いを浮き彫りにしてしまった。母親は、深く、まるで井戸の底を読むかのように考え込んだ。そして重い口が開く。
「一日、検討させてください」
まさか、だとすれば理由は一つだ。私はそっと声をかけた。
「ご主人様の確認ですよね」
「はい。そうです。私も息子もこの物件で良いと思っています。ただ、一度主人に確認してからお返事したいです」
「もちろん大丈夫です。私もご主人様を気にしていました。ただ、この物件は現在も募集中です。今この瞬間も、他の不動産会社でご紹介されている可能性もあります。山田様なら大丈夫だと思いますが、事前に申込書をご記入いただき、入居審査だけでも進めておきませんか」
私はこの物件を逃せば、同等のものを紹介する自信はない。その現実が、喉の奥を冷たく締めつける。母親が不安そうに尋ねる。
「お金は、発生しませんか?」
「はい。もちろん費用はかかりません。ただ、管理会社様の手前、本日の夜七時までにはご連絡いただければ助かります」
「わかりました。配慮ありがとうございます。必ず連絡します」
母親は丁寧に頭を下げ、そのまま申し込みの手続きに入った。紙の擦れる音が、やけに大きく店内に響く。胸の奥で、鼓動だけが一定のリズムを刻んでいた。ここまでが限界だ。出せるものはすべて出し切った。もう一歩も前へ踏み出せない。あとは、この一筆が運を呼ぶのか、それとも遠ざけるのか。
指先一つ触れられない場所で、勝敗が静かに決まろうとしている。私はただ、その瞬間を息を殺して待つしかなかった。
つづく。