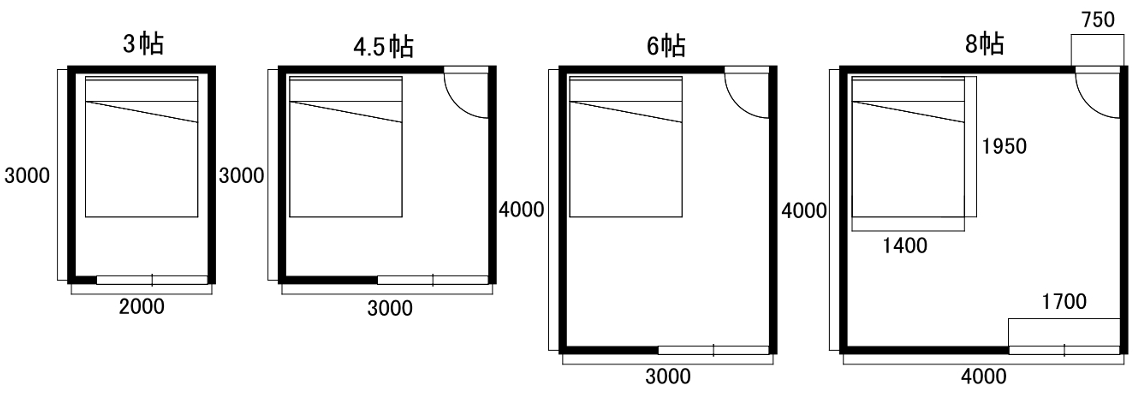私の偏愛--不動産エージェント(賃貸)十三章
本日の手続きが終わり、帰り際に声をかける。
「本日はご来店いただき誠にありがとうございました。条件や審査のことなど、少し込み入ったお話もしましたが、何かご不安はありませんか?」
「大丈夫です。今晩、主人に話をしてみます」
「ありがとうございます。本日の夜七時ごろ、山田様からのお電話をお待ちしております。何かございましたら、どんな些細なことでもご相談ください」
「本日はありがとうございました。前村さん、送迎お願いします」
三人の背中が窓越しの光の中に溶けていく。その姿を見送りながら、胸の奥で、心臓が静かにリズムを刻む。今期、背水の陣で挑む目標まであと一本。そのご返事まで、四時間を切っていた。
店長席に腰を下ろしたものの、今日一日の反響、来店予定、入金管理。普段なら淡々とこなせる事務作業に集中できない。心がどこか遠くにあり、夜に待つ“答え”だけが胸の奥でざわついていた。
頭の片隅で、先ほどの応対が再生される。挨拶、物件選定、案内の順路。どこかに見落としはなかったか。些細なミスひとつで申し込みが崩れることを、私は何度も痛いほど経験している。
気付けばまたキャビネットを開け、物件カードを一枚ずつ指でなぞるように見直していた。やはり東三方が最適だ。そう思いかけたとき、胸の奥で微かなざわめきが生まれる。
前提条件が変わったらどうなる?
問いが問いを呼び、思考の迷路は深まる。半田町の物件、外観だけの巡回。あれは父親の希望だったのか。あの案内だけでは薄かったのではないか。母親は、最終的には息子の意見に合わせ落ち着いた。しかし父親はどうなのか。胸の奥の不安は、冷たい波のように押し寄せては消えていく。東三方でそのまま契約になれば問題はない。しかし、もしそうでなかったときは、慌てず、冷静に対処しよう。そう自分に言い聞かせた。
プルルルル。店内に電話の音が響く。デスプレイにはお客様の番号。「あれ、予定の時間より一時間も早い」。とっさに私は
「私が出る。出るな」
自分でも驚くほどはっきりした声が店内に響いた。受話器を耳に当てると、母親の落ち着いた声が流れてくる。
「本日はありがとうございました。家族で話し合った結果」
心臓がひとつ強く跳ねた。
「まだ迷っていまして。申し訳ございません」
その瞬間、血の気がすうっと引く。
「いかがされましたか」
自分の声が、わずかに震えて聞こえた。母親は言う。
「主人が、家賃が高いのではと」
そうか。受付で聞いた「五万円まで」という数字。あれはザックリとした“表向きの予算”だったのか。本音は四万五千円前後。だから初回、半田町の四万六千円に反応したのだ。私は切り込んだ。
「では、初めにお問い合わせいただいた半田町の物件はいかがでしょうか。あちらは現在四万六千円です。また家主さまと弊社は長いお付き合いがございます。三千円ほどであれば、価格交渉も可能です」
さらに一息で続ける。
「本日は、東三方に強く気持ちが向いていたため、半田町の物件は周辺のみのご案内でした。明日、半田町の室内を実際にご覧いただくのはいかがでしょうか」
「少々お待ちください」
保留音のグリーンスリーブスが店内に広がる。静寂の中で、胸の鼓動だけがやけに大きく響く。十数秒後。
「ありがとうございます。明日、主人が午前中休みを取れるそうなので、三人でお伺いします。東四方町と半田町の両方、もう一度見せてください」
私は息を整え、歯切れよく答えた。
「はい、ありがとうございます。では明日十時、店頭でお待ちしております。どうぞお気を付けてお越しくださいませ」
電話を切る。危なかった、ギリギリ間に合った。“ギリギリ間に合った”とは、まだキャンセルの言葉が出ていないということ。ここが分岐点だ。迷いの段階ならば、条件交渉も提案もお客様の中で進行中。だが“キャンセル”の一言が出た瞬間、物件も営業も、お客様の中で過去になる。過去になってしまったものをよみがえらせるのは、ほぼ不可能だ。
また電話での無理押しは厳禁。焦りは言葉に滲み、信用を損なう。だからこそ、焦らず再来店へつなげる。手間を惜しまない姿勢こそ、お客様との信頼につながる。賃貸契約は大きな出費を伴う。迷うのは自然なこと。迷わない方が、むしろ不自然だ。
気付けば、営業担当たちの視線がこちらに集まっている。私は静かに、胸の奥でつぶやいた。これが賃貸仲介の営業だ。しっかり見ておけ。
つづく。